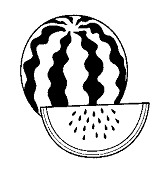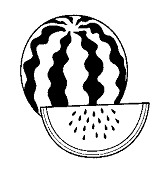
塩分の制限の仕方
血圧のコントロールのためには塩分の制限が大事ですが、それが簡単ではありません。まず、食材中の塩分が多いのに困ります。もともと含まれていますので、調理で除くとしても限界があります。また外食は味付けが辛いので、メニューに注意しても相当な塩分を取ってしまいます。
それに慣れの問題があります。子供の頃、私はスイカに塩をふりかけて美味しいと感じていました。今では何であんなことしていたのかと思いますが、おそらく皆がそうしていたからで、要するに習慣だろうと思います。意識して減塩しないと、辛いのが普通に感じます。
高血圧の方は、1日にとる塩分の量は6グラム以下が原則ですが、達成するためには常識を外れるほどの制限が必要です。普通の人は減塩したつもりでも10グラム以上を摂っていることが多いからです。高血圧の人の場合、漬け物を食べる、自分でしょうゆをかけるなどしていては、血圧をコントロールできることはまずないようです。納豆にもタレをつけないくらいの極端な制限が必要かもしれません。他の食材の塩分が多いので仕方ないと思います。
保健所や病院で減塩教室をやっていたら、一度参加してみられてはいかがでしょうか。味噌汁に含まれる塩分量を保ったまま、麹などを除いて塩分だけを飲んでみると、その辛さに驚きます。甘みと塩分が混ざった食品は想像以上に塩分を含んでいますが、甘さでマスクされて自分の舌の感覚だけでは辛いと感じることができません。塩分の含有量を勉強して、頭を使って制限する必要があります。
味噌汁1杯に1.5〜2.0グラム、つけ物2切れには1グラムくらいの塩分が含まれているそうです。お店で食べる麺類、定食類には5グラム以上の塩分が含まれると書いてある本もあります。1食で1日分の塩分になりそうです。それらを食べながら1日6グラム以下の塩分に収めるにはどうしたらよいか、私も分りません。たぶん私の感覚でやれる程度より、もっと制限しないといけないのでしょう。常識的な制限ではダメだと思います。
ある書物によれば、人間は1日に1グラムほどの塩分で生きていけるそうですが、実際には老人病院などで塩分を制限すると血液中の塩分が少なくなる人もいますので、やみくもに制限すれば良いわけではありません。血液中の塩分濃度の調節能力には個人差がありますので、減らすとしても急激に変化させず血液検査などで確認しながら、ゆっくり体を適応させるべきだと思います。
診療所便りより 平成18年8月 院長 橋本泰嘉